生き残った男の子
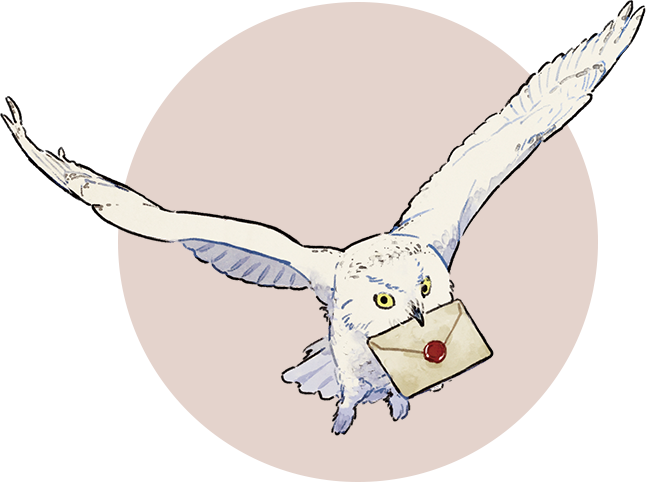
プリベット通り四番地の住人ダーズリー夫妻は、「おかげさまで、私どもはどこから見てもまともな人間です」というのが自慢だった。不思議とか神秘とかそんな非常識はまるっきり認めない人種で、まか不思議な出来事が彼らの周辺で起こるなんて、とうてい考えられなかった。
ダーズリー氏は、穴あけドリルを製造しているグラニングズ社の社長だ。ずんぐりと肉づきのよい体型のせいで、首がほとんどない。そのかわり巨大な口ひげが目立っていた。奥さんのほうはやせて、金髪で、なんと首の長さが普通の人の二倍はある。垣根越しにご近所の様子を詮索するのが趣味だったので、鶴のような首は実に便利だった。ダーズリー夫妻にはダドリーという男の子がいた。どこを探したってこんなに出来のいい子はいやしない、というのが二人の親ばかの意見だった。
そんな絵に描いたように満ち足りたダーズリー家にも、たった一つ秘密があった。何より怖いのは、誰かにその秘密をかぎつけられることだった。
―あのポッター一家のことが誰かに知られてしまったら、一巻の終わりだ。
ポッター夫人はダーズリー夫人の実の妹だが、二人はここ数年、一度も会ってはいなかった。それどころか、ダーズリー夫人は妹などいないというふりをしていた。何しろ、妹もそのろくでなしの夫も、ダーズリー家の家風とはまるっきり正反対だったからだ。
―ポッター一家がふいにこのあたりに現れたら、ご近所の人たちがなんと言うか、考えただけでも身の毛がよだつ。
ポッター一家にも小さな男の子がいることを、ダーズリー夫妻は知ってはいたが、ただの一度も会ったことがない。
―そんな子と、うちのダドリーが関わり合いになるなんて……。
それもポッター一家を遠ざけている理由の一つだった。
さて、ある火曜日の朝のことだ。ダーズリー一家が目を覚ますと、外はどんよりとした灰色の空だった。物語はここから始まる。まか不思議なことがまもなくイギリス中で起ころうとしているなんて、そんな気配は曇り空のどこにもなかった。ダーズリー氏は鼻歌まじりで、仕事用の思いっきりありふれた柄のネクタイを選んだ。奥さんのほうは大声で泣きわめいているダドリー坊やをやっとこさベビーチェアに座らせ、嬉々としてご近所のうわさ話を始めた。
窓の外を、大きなふくろうが羽ばたいて通り過ぎたが、二人とも気がつかなかった。八時半、ダーズリー氏は鞄を持ち、奥さんのほおにちょこっとキスして、それからダドリー坊やにもバイバイのキスをしようとしたが、しそこなった。坊やがかんしゃくを起こして、コーンフレークを皿ごと壁に投げつけている最中だったからだ。「わんぱく坊主め」ダーズリー氏は満足げに笑いながら家を出て、自家用車に乗り込み、四番地の路地をバックで出ていった。広い通りに出る前の角の所で、ダーズリー氏は初めて、何かおかしいぞと思った。
―なんと猫が地図を見ている―ダーズリー氏は一瞬、目を疑うたがった。もう一度よく見ようと急いで振り返ると、確かにプリベット通りの角にトラ猫が一匹立ち止まっていた。しかし、地図のほうは見えなかった。ばかな、いったい何を考えているんだ。きっと光のいたずらだったにちがいない。ダーズリー氏は瞬きをして、もう一度猫をよく見なおした。猫は見つめ返した。角を曲がり、広い通りに出たとき、バックミラーに映っている猫が見えた。なんと、今度は「プリベット通り」と書かれた標識を読んでいる―いや、「見て」いるだけだ。猫が地図やら標識やらを読めるはずがない。ダーズリー氏は体をブルッと振って気をとりなおし、猫のことを頭の中から振り払った。街に向かって車を走らせているうちに、彼の頭は、その日に取りたいと思っている穴あけドリルの大口注文のことでいっぱいになった。
ところが、街はずれまで来たとき、ドリルなど頭から吹っ飛ぶようなことが起こったのだ。いつもの朝の渋滞にまきこまれ、車の中でじっとしていると、奇妙な服を着た人たちがうろうろしているのが、いやでも目についた。マントを着ている。
―おかしな服を着た連中にはがまんがならん―近ごろの若いやつらの格好ときたら! マントも最近のばかげた流行なんだろう。
ハンドルを指でいらいらとたたいていると、ふと、すぐそばに立っているおかしな連中が目に留まった。何やら興奮してささやき合っている。けしからんことに、とうてい若いとはいえないやつがひと組まじっている。
―あの男なんか自分より年をとっているのに、エメラルド色のマントを着ている。どういう神経だ!
まてよ。ダーズリー氏は、はたと思いついた。
―くだらん芝居をしているにちがいない―きっと、連中は寄付集めをしているんだ……そうだ、それだ!
やっと車が流れはじめた。数分後、車はグラニングズ社の駐車場に着き、ダーズリー氏の頭は穴あけドリルに戻っていた。
ダーズリー氏のオフィスは十階で、いつも窓に背を向けて座っていた。そうでなかったら、今朝は穴あけドリルに集中できなかったかもしれない。真っ昼間からふくろうが空を飛び交うのを、ダーズリー氏は見ないですんだが、道行く多くの人はそれを目撃した。ふくろうが次から次へと飛んで行くのを指さしては、いったいあれはなんだと口をあんぐりあけて見つめていたのだ。ふくろうなんて、たいがいの人は夜にだって見たことがない。一方ダーズリー氏は、昼までしごくまともに、ふくろうとは無縁で過ごした。五人の社員をどなりつけ、何本か重要な電話をかけ、また少しガミガミどなった。おかげで昼までは上機嫌だった。それから、少し手足を伸ばそうかと、道路のむかい側にあるパン屋まで歩いて買い物に行くことにした。
マントを着た連中のことはすっかり忘れていたのに、パン屋の手前でまたマント集団に出会ってしまった。そばを通り過ぎるとき、ダーズリー氏は、けしからんとばかりににらみつけた。しかし、なぜかこの連中は、ダーズリー氏を不安な気持ちにさせた。このマント集団も、何やら興奮してささやき合っていた。しかも、寄付集めの空き缶が一つも見当たらない。パン屋からの帰り道、大きなドーナツを入れた紙袋を握り、また連中のそばを通り過ぎようとしたそのとき、こんな言葉が耳に飛び込んできた。
「ポッターさんたちが、そう、わたしゃそう聞きました……」
「……そうそう、息子のハリーがね……」
ダーズリー氏はハッと立ち止まった。恐怖が湧き上がってきた。いったんはヒソヒソ声のするほうを振り返って、何か言おうかと思ったが、まてよ、と考えなおした。
ダーズリー氏は猛スピードで道を横切り、オフィスに駆け戻るや否や、秘書に「誰も取り継ぐな」と命令し、ドアをピシャッと閉めて電話をひっつかみ、家の番号を回しはじめた。しかし、ダイヤルし終わらないうちに気が変わった。受話器を置き、口ひげをなでながら、ダーズリー氏は考えた。
―まさか。自分はなんて愚かなんだ。ポッターなんてめずらしい名前じゃない。ハリーという名の男の子がいるポッター家なんて、山ほどあるにちがいない。考えてみりゃ、甥の名前がハリーだったかどうかさえ確かじゃない。一度も会ったこともないし、ハービーという名だったかもしれない。いやハロルドかも。こんなことで妻に心配をかけてもしょうがない。妹の話がちらっとでも出ると、あれはいつも取り乱す。無理もない。もし自分の妹があんなふうだったら……それにしても、いったいあのマントを着た連中は……。
昼からは、どうも穴あけドリルに集中できなかった。五時に会社を出たときも、何かが気になり、外に出たとたん誰かと正面衝突してしまった。
「すみません」
ダーズリー氏はうめき声を出した。相手は小さな老人で、よろけて転びそうになっていた。
数秒後、ダーズリー氏は老人がスミレ色のマントを着ているのに気づいた。地面にばったりと這いつくばりそうになったのに、まったく気にしていない様子だ。それどころか、顔が上下に割れるかと思うほど大きくニッコリして、道行く人が振り返るほどのキーキー声でこう言った。
「旦那、すみませんなんてとんでもない。今日は何があったって気にしませんよ。ばんざい! 『例のあの人』がとうとういなくなったんですよ! あなたのようなマグルも、こんな幸せなめでたい日はお祝いすべきです」
小さな老人はダーズリー氏のおへそのあたりをいきなりギュッと抱きしめると、立ち去っていった。ダーズリー氏はその場に根が生えたように突っ立っていた。まったく見ず知らずの人に抱きつかれた。マグルとかなんとか呼ばれたような気もする。くらくらしてきた。急いで車に乗り込むと、ダーズリー氏は家に向かって走りだした。どうか自分の幻想でありますように……幻想などけっして認めないダーズリー氏にしてみれば、こんな願いを持つのは生まれて初めてだった。
やっとの思いで四番地に戻ると、真っ先に目に入ったのは―ああ、なんたることだ―今朝見かけた、あの、トラ猫だった。今度は庭の石垣の上に座り込んでいる。まちがいなくあの猫だ。目のまわりの模様がおんなじだ。
「シッシッ!」
ダーズリー氏は大声を出した。
猫は動かない。じろりとダーズリー氏を見ただけだ。まともな猫がこんな態度をとるものだろうか、と彼は首をかしげた。それから気をしゃんと取りなおし、家に入っていった。妻には何も言うまいという決心は変わっていなかった。奥さんは、すばらしくまともな一日を過ごしていた。夕食を食べながら、隣のミセスなんとかが娘のことでさんざん困っているとか、ダドリー坊やが「イヤッ!」という新しい言葉を覚えたとかを夫に話して聞かせた。ダーズリー氏はなるべくふだんどおりに振る舞おうとした。ダドリー坊やが寝たあと、居間に移ったところで、ちょうどテレビの最後のニュースが始まった。
「さて最後のニュースです。全国のバードウォッチャーによれば、今日はイギリス中のふくろうがおかしな行動を見せたとのことです。通常、ふくろうは夜に狩をするので、昼間に姿を見かけることはめったにありませんが、今日は夜明けとともに、何百というふくろうが四方八方に飛び交う光景が見られました。なぜふくろうの行動が急に夜昼逆になったのか、専門家たちは首をかしげています」
そこでアナウンサーはニヤリと苦笑いした。
「ミステリーですね。ではお天気です。ジム・マックガフィンさんどうぞ。ジム、今夜もふくろうが降ってきますか?」
「テッド、そのあたりはわかりませんが、今日おかしな行動をとったのはふくろうばかりではありませんよ。視聴者のみなさんが、遠くはケント、ヨークシャー、ダンディー州からお電話をくださいました。きのう、私は雨の予報を出したのに、かわりに流れ星がどしゃ降りだったそうです。たぶん早々と『ガイ・フォークスの焚き火祭り』でもやったんじゃないでしょうか。みなさん、祭りの花火は来週ですよ! いずれにせよ、今夜はまちがいなく雨でしょう」
安楽椅子の中でダーズリー氏は体が凍りついたような気がした。イギリス中で流れ星だって? 真っ昼間からふくろうが飛んだ? マントを着た奇妙な連中がそこいら中にいた? それに、あのヒソヒソ話。ポッター一家がどうしたとか……。
奥さんが紅茶を二つ持って居間に入ってきた。まずい。妻に何か言わなければなるまい。
ダーズリー氏は落ち着かない咳払いをした。
「あー、ペチュニアや。ところで最近、おまえの妹から便りはなかったろうね」
案の定、奥さんはびくっとして怒った顔をした。二人ともふだん、奥さんに妹はいないということにしているのだから当然だ。
「ありませんよ。どうして?」
とげとげしい返事だ。
「おかしなニュースを見たんでね」
ダーズリー氏はもごもご言った。
「ふくろうとか……流れ星だとか……それに、今日、街に変な格好をした連中がたくさんいたんでな」
「それで?」
「いや、ちょっと思っただけだがね……もしかしたら……何か関わりがあるかと……その、なんだ……あれの仲間と」
奥さんは口をすぼめて紅茶をすすった。ダーズリー氏は「ポッター」という名前を耳にした、と思いきって打ち明けるべきかどうか迷ったが、やはりやめることにした。そのかわり、できるだけさりげなく聞いた。
「あそこの息子だが……確かうちのダドリーと同じくらいの年じゃなかったかね?」
「そうかも」
「なんという名前だったか……。確かハワードだったね」
「ハリーよ。私に言わせりゃ、下品でありふれた名前ですよ」
「ああ、そうだった。おまえの言うとおりだよ」
ダーズリー氏はすっかり落ち込んでしまった。二人で二階の寝室に上がっていくときも、彼はまったくこの話題には触れなかった。
奥さんがトイレに行ったすきに、こっそり寝室の窓に近寄り、家の前をのぞいてみた。あの猫はまだそこにいた。何かを待っているように、プリベット通りの奥のほうをじっと見つめている。
―これも自分の幻想なのか? これまでのことは何もかもポッター一家と関わりがあるのだろうか? もしそうなら……もし自分たちがあんな夫婦と関係があるなんてことが明るみに出たら……ああ、そんなことには耐えられない。
ベッドに入ると、奥さんはすぐに寝入ってしまったが、ダーズリー氏はあれこれ考えて寝つけなかった。
―しかし、万々が一ポッターたちが関わっていたにせよ、あの連中が自分たちの近くにやってくるはずがない。あの二人やあの連中のことをわしらがどう思っているか、ポッター夫妻は知っているはずだ……何が起こっているかは知らんが、わしやペチュニアが関わり合いになることなどありえない―そう思うと少しホッとして、ダーズリー氏はあくびをして寝返りを打った。
―わしらにかぎって、絶対に関わり合うことはない……。
―なんという大まちがい―。
ダーズリー氏がとろとろと浅い眠りに落ちたころ、塀の上の猫は眠る気配さえ見せていなかった。銅像のようにじっと座ったまま、瞬きもせずプリベット通りの奥の曲がり角を見つめていた。隣の道路で車のドアをバタンと閉める音がしても、二羽のふくろうが頭上を飛び交っても、毛一本動かさない。真夜中近くになって、初めて猫は動いた。
猫が見つめていたあたりの曲がり角に、一人の男が現れた。あんまり突然、あんまりスーッと現れたので、地面から湧いて出たかと思えるぐらいだった。猫はしっぽをピクッとさせて、目を細めた。
プリベット通りで、絶対にこんな人を見かけるはずがない。ひょろりと背が高く、髪やひげの白さから見て相当の年寄りだ。髪もひげもあまりに長いので、ベルトにはさみ込んでいる。
ゆったりと長いローブの上に、地面を引きずるほどの長い紫のマントをはおり、かかとの高い、留め金飾りのついたブーツをはいている。明るいブルーの眼が、半月形のめがねの奥でキラキラ輝き、高い鼻が途中で少なくとも二回は折れたように曲がっている。この人の名はアルバス・ダンブルドア。
名前も、ブーツも、何から何までプリベット通りらしくない。しかし、ダンブルドアはまったく気にしていないようだった。マントの中をガサゴソとせわしげに何か探していたが、誰かの視線に気づいたらしく、ふっと顔を上げ、通りのむこうからこちらの様子をじっとうかがっている猫を見つけた。そこに猫がいるのがなぜかおもしろいらしく、クスクスと笑うと、「やっぱりそうか」とつぶやいた。
探していたものが内ポケットから出てきた。銀のライターのようだ。ふたをパチンと開け、高くかざして、カチッと鳴らした。
一番近くの街灯が、ポッと小さな音を立てて消えた。
もう一度カチッといわせた。
次の街灯がゆらめいて闇の中に消えていった。「灯消けしライター」を十二回カチカチ鳴らすと、十二個の街灯は次々と消え、残る灯りは、遠くの、針の先でつついたような二つの点だけになった。猫の目だ。まだこっちを見つめている。いま誰かが窓の外をのぞいても、好奇心で目を光らせたダーズリー夫人でさえ、何が起こっているのか、この暗闇ではまったく見えなかっただろう。ダンブルドアは「灯消けしライター」をマントの中にスルリとしまい、四番地のほうへと歩いた。そして塀の上の猫の隣に腰かけた。ひと息おくと、顔は向けずに、猫に向かって話しかけた。
「マクゴナガル先生、こんな所で奇遇じゃのう」
トラ猫のほうに顔を向け、ほほえみかけると、猫はすでに消えていた。かわりに、厳格そうな女の人が、あの猫の目の周りにあったしま模様とそっくりの四角いめがねをかけて座っていた。やはりマントを、しかもエメラルド色のを着ている。黒い髪をひっつめて、小さな髷にしている。
「どうして私だとおわかりになりましたの?」
女の人は見破られて動揺していた。
「まあまあ、先生。あんなにコチコチな座り方をする猫なんていやしませんぞ」
「一日中れんが塀の上に座っていればコチコチにもなります」
「一日中? お祝いしておればよかったじゃろうに。ここに来る途中、お祭りやらパーティやら、ずいぶんたくさん見ましたぞ」
マクゴナガル先生は怒ったようにフンと鼻を鳴らした。
「ええ、確かにみんな浮かれていますね」
マクゴナガル先生はいらいらした口調だ。
「みんなもう少し慎重になるべきだとはお思いになりませんか? まったく……マグルたちでさえ、何かあったと感づきましたよ。何しろニュースになりましたから」
マクゴナガル先生は灯りの消えたダーズリー家の窓をあごでしゃくった。
「この耳で聞きましたよ。ふくろうの大群……流星群……そうなると、マグルの連中もまったくのおばかさんじゃありませんからね。何か感づかないはずはありません。ケント州の流星群だなんて―ディーダラス・ディグルのしわざですわ。あの男はいつだって軽はずみなんだから」
「みんなを責めるわけにはいかんじゃろう」
ダンブルドアはやさしく言った。
「この十一年間、お祝いごとなぞほとんどなかったのじゃから」
「それはわかっています」
マクゴナガル先生は腹立たしげに言った。
「だからといって、分別を失ってよいわけはありません。みんな、なんて不注意なんでしょう。真っ昼間から街に出るなんて。しかもマグルの服に着替えもせずに、あんな格好のままでうわさ話をし合うなんて」
ダンブルドアが何か言ってくれるのを期待しているかのように、マクゴナガル先生はちらりと横目でダンブルドアを見たが、何も反応がないので、話を続けた。
「よりによって、『例のあの人』がついに消え失せたちょうどその日に、今度はマグルが私たちに気づいてしまったらとんでもないことですわ。ダンブルドア先生、『あの人』は本当に消えてしまったのでしょうね?」
「確かにそうらしいのう。我々は大いに感謝しなければ。レモンキャンディはいかがかな?」
「なんですって?」
「レモンキャンディじゃよ。マグルの食べる甘い物じゃが、わしゃ、これが好きでな」
「けっこうです」
レモンキャンディなど食べている場合ではないとばかりに、マクゴナガル先生は冷ややかに答えた。
「いま申し上げましたように、たとえ『例のあの人』が消えたにせよ……」
「まあまあ、先生、あなたのように見識のおありになる方が、彼を名指しで呼べないわけはないでしょう? 『例のあの人』なんてまったくもってナンセンス。この十一年間、ちゃんと名前で呼ぶようみんなを説得し続けてきたのじゃが。『ヴォルデモート』とね」
マクゴナガル先生はぎくりとしたが、ダンブルドアはくっついたレモンキャンディをはがすのに夢中で気づかないようだった。
「『例のあの人』なんて呼び続けたら、混乱するばかりじゃよ。ヴォルデモートの名前を言うのが恐ろしいなんて、理由がないじゃろうが」
「そりゃ、先生にとってはないかもしれませんが」
マクゴナガル先生は驚きと尊敬の入りまじった言い方をした。
「だって、先生はみんなとはちがいます。『例のあ』……いいでしょう、ヴォルデモートが恐れていたのはあなた一人だけだったということは、みんな知っていますよ」
「おだてないでおくれ」
ダンブルドアは静かに言った。
「ヴォルデモートには、わしにはけっして持つことができない力があった」
「それは、あなたがあまりに―そう……気高くて、そういう力を使おうとなさらなかったからですわ」
「あたりが暗くて幸いじゃよ。こんなに赤くなったのはマダム・ポンフリーがわしの新しい耳あてをほめてくれたとき以来じゃ」
マクゴナガル先生は鋭いまなざしでダンブルドアを見た。
「ふくろうが飛ぶのは、うわさが飛ぶのに比べたらなんでもありませんよ。みんながどんなうわさをしているか、ご存じですか? なぜ彼が消えたのだろうとか、何が彼にとどめを刺したのだろうかとか」
マクゴナガル先生はいよいよ核心に触れたようだ。一日中冷たい、固い塀の上で待っていた本当のわけはこれだ。猫に変身していたときも、自分の姿に戻ったときにも見せたことがない、射るようなまなざしで、ダンブルドアを見すえている。ほかの人がなんと言おうが、ダンブルドアの口から聞かないかぎり、絶対信じないという目つきだ。ダンブルドアは何も答えず、レモンキャンディをもう一個取り出そうとしていた。
「みんながなんとうわさしているかですが……」
マクゴナガル先生はもうひと押ししてきた。
「昨夜、ヴォルデモートがゴドリックの谷に現れた。ポッター一家がねらいだった。うわさではリリーとジェームズが……ポッター夫妻が……あの二人が……死んだ……とか」
ダンブルドアはうなだれた。マクゴナガル先生は息をのんだ。
「リリーとジェームズが……信じられない……信じたくなかった……ああ、アルバス……」
ダンブルドアは手を伸ばしてマクゴナガル先生の肩をそっとたたいた。
「わかる……よーくわかるよ……」
沈痛な声だった。
マクゴナガル先生は声を震わせながら話し続けた。
「それだけじゃありませんわ。うわさでは、一人息子のハリーを殺そうとしたとか。でも―失敗した。その小さな男の子を殺すことはできなかった。なぜなのか、どうなったのかはわからないが、ハリー・ポッターを殺しそこねたとき、ヴォルデモートの力が打ち砕かれた―だから彼は消えたのだと、そういううわさです」
ダンブルドアはむっつりとうなずいた。
「それじゃ……やはり本当なんですか?」
マクゴナガル先生は口ごもった。
「あれほどのことをやっておきながら……あんなにたくさん人を殺したのに……小さな子供を殺しそこねたって言うんですか? 驚異ですわ……よりによって、彼にとどめを刺したのは子供……それにしても、一体全体ハリーはどうやって生き延びたんでしょう?」
「想像するしかないじゃろう。本当のことはわからずじまいかもしれん」
マクゴナガル先生はレースのハンカチを取り出し、めがねの下から眼に押し当てた。ダンブルドアは大きく鼻をすすると、ポケットから金時計を取り出して時間を見た。とてもおかしな時計だ。針は十二本もあるのに、数字が書いていない。そのかわり、小さな惑星がいくつも時計の縁を回っていた。ダンブルドアにはこれでわかるらしい。時計をポケットにしまうと、こう言った。
「ハグリッドは遅いのう。ところで、あの男じゃろう? わしがここに来ると教えたのは」
「そうです。一体全体なぜこんな所においでになったのか、たぶん話してはくださらないのでしょうね?」
「ハリー・ポッターを、おばさん夫婦の所へ連れてくるためじゃよ。親せきはそれしかいないのでな」
「まさか―まちがっても、ここに住んでいる連中のことじゃないでしょうね」
マクゴナガル先生ははじかれたように立ち上がり、四番地を指さしながら叫んだ。
「ダンブルドア、だめですよ。今日一日ここの住人を見ていましたが、ここの夫婦ほど私たちとかけはなれた連中はまたといませんよ。それにここの息子ときたら―母親がこの通りを歩いているとき、お菓子が欲しいと泣きわめきながら母親を蹴り続けていましたよ。ハリー・ポッターがここに住むなんて!」
「ここがあの子にとって一番いいのじゃ」
ダンブルドアはきっぱりと言った。
「おじさんとおばさんが、あの子が大きくなったらすべてを話してくれるじゃろう。わしが手紙を書いておいたから」
「手紙ですって?」
マクゴナガル先生は力なくそうくり返すと、また塀に座りなおした。
「ねえ、ダンブルドア。手紙でいっさいを説明できるとお考えですか? 連中は絶対あの子のことを理解しやしません! あの子は有名人です―伝説の人です―今日のこの日が、いつかハリー・ポッター記念日になるかもしれない―ハリーに関する本が書かれるでしょう―私たちの世界でハリーの名を知らない子供は一人もいなくなるでしょう!」
「そのとおり」
ダンブルドアは半月めがねの上から真面目な目つきをのぞかせた。
「そうなればどんな少年でも舞い上がってしまうじゃろう。歩いたりしゃべったりする前から有名だなんて! 自分が覚えてもいないことのために有名だなんて! あの子に受け入れる準備ができるまで、そうしたことからいっさい離れて育つほうがずっといいということがわからんかね?」
マクゴナガル先生は口を開きかけたが、思いなおして、のどまで出かかった言葉をのみ込んだ。
「そう、そうですね。おっしゃるとおりですわ。でもダンブルドア、どうやってあの子をここに連れてくるんですか?」
ダンブルドアがハリーをマントの下に隠しているとでも思ったのか、マクゴナガル先生はちらりとマントに目をやった。
「ハグリッドが連れてくるよ」
「こんな大事なことをハグリッドに任せて―あの……賢明なことでしょうか?」
「わしは自分の命でさえハグリッドに任せられるよ」
「何もあれの心根がまっすぐじゃないなんて申しませんが」
マクゴナガル先生はしぶしぶ認めた。「でもご存じのように、うっかりしているでしょう。どうもあれときたら―おや、何かしら?」
低いゴロゴロという音があたりの静けさを破った。二人が通りの端から端まで、車のヘッドライトが見えはしないかと探している間に、音は確実に大きくなってきた。二人が同時に空を見上げたときには、音は爆音になっていた。―大きなオートバイが空からドーンと降ってきて、二人の目の前に着陸した。
巨大なオートバイだったが、それにまたがっている男に比べればちっぽけなものだ。男の背丈は普通の二倍、横幅は五倍はある。許しがたいほど大きすぎて、それになんて荒々しい―ぼうぼうとした黒い髪とひげが、長くもじゃもじゃとからまり、ほとんど顔中を覆っている。手はごみバケツのふたほど大きく、革ブーツをはいた足は赤ちゃんイルカぐらいある。筋肉隆々の巨大な腕に、何か毛布にくるまったものを抱えていた。
「ハグリッドや」
ダンブルドアはホッとしたような声で呼びかけた。
「やっと来たのう。いったいどこからオートバイを手に入れたのかね?」
「借りたんでさ。ダンブルドア先生さま」
大男はそうっと注意深くバイクから降りた。
「ブラック家の息子のシリウスが借してくれたんで。先生、この子を連れてきました」
「問題はなかったろうね?」
「はい、先生。家はあらかた壊されっちまってたですが、マグルたちが群れ寄ってくる前に、無事に連れ出しました。ブリストルの上空を飛んどったときに、この子は眠っちまいました」
ダンブルドアとマクゴナガル先生は、毛布の包みの中をのぞき込んだ。かすかに、男の赤ん坊が見えた。ぐっすり眠っている。漆黒のふさふさした前髪、そして額には不思議な形の傷が見えた。稲妻のような形だ。
「この傷があの……」マクゴナガル先生がささやいた。
「そうじゃ。一生残るじゃろう」
「ダンブルドア、なんとかしてやれないんですか?」
「たとえできたとしても、わしは何もせんよ。傷はけっこう役に立つものじゃ。わしにも一つ左ひざの上にあるがね、完全なロンドンの地下鉄地図になっておる……さてと、ハグリッドや、その子をこっちへ―早くすませたほうがよかろう」
ダンブルドアはハリーを腕に抱き、ダーズリー家のほうに行こうとした。
「あの……先生、お別れのキスをさせてもらえねえでしょうか?」
ハグリッドが頼んだ。
大きな毛むくじゃらの顔をハリーに近づけ、ハグリッドはチクチク痛そうなキスをした。そして突然、傷ついた犬のような声でワオーンと泣きだした。
「シーッ! マグルたちが目を覚ましてしまいますよ」
マクゴナガル先生が注意した。
「す、す、すまねえ」
しゃくりあげながらハグリッドは大きな水玉模様のハンカチを取り出し、その中に顔をうずめた。
「と、とってもがまんできねえ……リリーとジェームズは死んじまうし、かわいそうなちっちゃなハリーはマグルたちと暮らさなきゃなんねえ……」
「そう、ほんとに悲しいことよ。でもハグリッド、自分を抑えなさい。さもないとみんなに見つかってしまいますよ」
マクゴナガル先生は小声でそう言いながら、ハグリッドの腕をやさしくポンポンとたたいた。
ダンブルドアは庭の低い生け垣をまたいで、玄関へと歩いていった。そっとハリーを戸口に置くと、マントから手紙を取り出し、ハリーをくるんだ毛布にはさみ込み、二人のところに戻ってきた。三人は、まるまる一分間そこにたたずんで、小さな毛布の包みを見つめていた。
ハグリッドは肩を震わせ、マクゴナガル先生は目をしばたたかせ、ダンブルドアの目からはいつものキラキラした輝きが消えていた。
「さてと……」
ダンブルドアがやっと口を開いた。
「これですんだ。もうここにいる必要はない。帰ってお祝いに参加しようかの」
「へい」
ハグリッドの声はくぐもっている。
「バイクは片づけておきますだ。マクゴナガル先生、ダンブルドア先生さま、おやすみなせえまし」
ハグリッドは流れ落ちる涙を上着のそででぬぐい、オートバイにさっとまたがり、エンジンをかけた。バイクは唸りを上げて空に舞い上がり、夜の闇へと消えていった。
「後ほどお会いしましょうぞ。マクゴナガル先生」
ダンブルドアはマクゴナガル先生のほうに向かってうなずいた。マクゴナガル先生は答えるかわりに鼻をかんだ。
ダンブルドアはくるりと背を向け、通りのむこうに向かって歩きだした。曲がり角で立ち止まり、また銀の「灯消けしライター」を取り出し、一回だけカチッといわせた。十二個の街灯がいっせいにともり、プリベット通りは急にオレンジ色に照らしだされた。トラ猫が道のむこう側の角をしなやかに曲がっていくのが見える。そして四番地の戸口の所には毛布の包みだけがぽつんと見えた。
「幸運を祈るよ、ハリー」
ダンブルドアはそうつぶやくと、靴のかかとでくるくるっと回転し、ヒュッというマントの音とともに消えた。
こぎれいに刈り込まれたプリベット通りの生け垣を、静かな風が波立たせた。墨を流したような夜空の下で、通りはどこまでも静かで整然としていた。まか不思議な出来事が、ここで起こるとは誰も思ってもみなかったことだろう。赤ん坊は眠ったまま、毛布の中で寝返えりを打った。片方の小さな手が、脇に置かれた手紙を握った。自分が特別だなんて知らずに、有名だなんて知らずに、ハリー・ポッターは眠り続けている。数時間もすれば、ダーズリー夫人が戸を開け、ミルクの空き瓶を外に出そうとしたとたん、悲鳴を上げるだろう。その声でハリーは目を覚ますだろう。それから数週間は、いとこのダドリーにこづかれ、つねられることになるだろうに……そんなことは何も知らずに、赤ん坊は眠り続けている……ハリーにはわかるはずもないが、こうして眠っているこの瞬間に、国中のあちこちでこっそりと集まった人々が、杯を挙げ、ヒソヒソ声で、こう言っているのだ。
「生き残った男の子、ハリー・ポッターに乾杯!」
